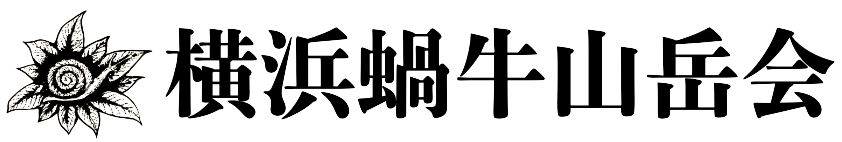| 日 程 | 2025年05月03日(土)-2025年05月06日(火) |
| ルート | 北アルプス 奥穂高南稜、前穂高岳 |
| メンバー | 山下先生、もっちゃん、塾長、なべたけ(記) |

いったんクライミングルートに出れば、気持ちだけではどうすることもできない、体力、知識、技術、経験、集中力など、さまざまな山への対応力が求められる。
しかし、なによりも、仲間への、山への気持ちが、いちばん大切であったことを再確認した山行だった。
3日 上高地(9:00)〜岳沢(13:00)〜ベースキャンプ設営〜雪上ロープトレ(15:00〜16:00)〜岳沢小屋幕営
雪上での支点の取り方、ビレイ法をメインに繰り返し指導してくださり、いつのまにか小1時間が過ぎたところで、気温も低下してきているなか、雪トレ終了。

出発前、塾長から沢渡を出発したというラインを確認。南稜の取り付きへ向かう。
早朝から青空が広がり、最高のクライミング日和になりそうだった。
雪渓を滝沢方面に向かうと、大滝手前の左上する雪渓沿いに取り付いている者や、南稜の末端部右側のルンゼ状のほうから取り付いているパーティーも見えた。ルンゼ状の取り付き部は、無雪期のトレースが判別できた。
先生のペースがやはり上がらず、体調はこの日も芳しくない様子だった。もっちゃん、なべたけから遅れて取り付き近くに登ってくると「俺はまだダメだな。ふたりで行ってこい。」とお声がかかった。
滝沢側の左上ラインは、雪渓が切れているところがあるのでやめたほうがいいと指導をもらい、末端部右側のトレースから取り付く。
出だしは雪がとけて夏道が露出していたが、すぐに雪面になった。慎重に、ペース良く登っていく。

先行パーティーに追いつく。やさしい岩場からロープを出してつるべ登攀に移った。
ゆっくり1峰の岩場を登っていく。
トリコニー内のルートファインディングに不安があったので、短めにピッチを切っていく。
もっちゃんリードで迷路のような通路状になっているチムニー内を右に折れて進み、ロープが止まった。難所があるのかもしれないと緊張感が高まっていた時、ビレイをしていたなべたけの後方からソロの女性が現れた。
ロープ伝いにもっちゃんの状況を感じつつ話をすると、広島から毎週北アルプスに登りに来ているとよく分からないことをおっしゃっていて、ソロということもありただものではない感があったのだが、一見、かわいらしいお姉様のようで、楽しい気持ちになってしまった。
その間、ゆるりゆるりとロープが出て行く。長い時間が過ぎ、ようやくビレイ解除のコールが聞こえた。
なべたけフォローでチムニー内を通り、外に出ると2〜3mほどの微妙なトラバース(岩場に残置ハーケンあり)後、3mほどだがかなり傾斜の強い雪壁の直登が待っていた。雪が緩んできており、一瞬足場がくずれてヒヤッとしたが、なんとか攀じ登る。雪壁の上でビレイをしているもっちゃんが、落ち着き払って迎えてくれた。
そして、なべたけのすぐ後から「こわい、こわい」と言いながらひとりぼっちさんが追いかけて登ってきた。お先にどうぞと促すが、こわいから後からついて行って良いですかとのこと。
なべたけリードでロープを伸ばし、リッジ状の小ピナクルを回り込んでピッチを切ると、ひとりぼっちさんがロープ沿いにフォローしてきた。小ピナクルを回り込む箇所が少し悪く感じたが、「こわい、こわい」と言いながら非常に軽い身のこなだった。
ビレイ点の先は、とりあえず悪場は見えず、アッセンダーを解除して先に進んでもらった。もっちゃんがフォローでビレイ点に到着したころには、2峰のピークに差し掛かっており、こちらのほうに声をかけて写真を撮ってくれた。ルーファイがいまいちで、かえって迷惑をかけてしまったかもしれない。

核心部を通過してホッとひと息をつくが、気持ちを切り替えて、慎重に雪稜のトレースを辿り、吊り尾根を目指す。
五月晴れの太陽の下、雪は緩んできていたが、完全に腐っているような状態ではなく、確実に標高を上げていくことができた。
ピークに近づいている高揚感が、天空から見守ってくれているであろう仲間の存在を、より鮮やかにしていたのかもしれない。
もっちゃん、なべたけともに、あふれ出てくる気持ちを感じていたのではと思う。
お昼すぎ、南稜の頭から奥穂高山頂へ。奥穂高の山頂で、約束を果たしたように手を合わせるもっちゃんの姿が印象的だった。ジャンダルムの勇姿も間近で、なべたけ仲間と共にした1年前の合宿を思い出していた。山頂は、私たち2人がいた間はほかに誰もおらず、風もなく、とても静かだった。
ここから吊り尾根〜前穂高岳〜奥明神沢下降の下山パート。前日は、重太郎新道経由での岳沢下山も話していたが、今朝、取り付きで先生と奥明神沢下降を確認していた。(岳沢小屋での情報によると、重太郎新道はトレースがない可能性が高かった。)
しかし…ここからの下山パートが、非常に長い道のりだった。吊尾根上は、ほぼ雪渓のトレース沿いに歩いたが、ところどころでトレースが途切れ、夏道沿いに進んでいたと思われるが、急斜面の雪渓トラバースを繰り返し、ペースは上がらず、次第に消耗していった。(下山後、先生に確認すると、トラバースではなく稜線にルートをとれば楽だったとのことだった。)

前穂山頂直下に到達したのが、すでに日没後。GPSで位置確認を繰り返しながら、紀美子平には向かわずに、山頂へ直登した。直登した広い尾根は、そこまでの斜度ではなく、雪面は、締まってきてはいたものの、しっかりアイゼンが刺さる状態だったが、もっちゃんからは「アイスクライミングだ〜!」とぼやきが聞かれ、ルーファイをするなべたけは、少しスミマセンと思いつつ、そのまま登り続けた。
20:00前穂高岳山頂。GPSで位置確認、進行する方角を慎重に確認しながら、奥明神沢から伸びてきているのであろう無数のトレースを辿り、奥明神沢へ入った。
日中にできたと思われるトレースは明瞭だったが、雪は夜が深まるとともに堅く締まってきていた。ミスすれば奈落の底へ急降下の斜度だったので、慎重を期してダガーポジションでの下降を延々と続けた。

日中であれば、おそらく柔らかい雪の状態で恐怖感は少ないが、数時間の違いで大きく状況が変わることを実感していた。
修行僧になった気持ちでダガーポジションを続けること数時間。疲労はピークを過ぎて、日付が変わってしまったことなどどうでもよい気持ちになるほどだった。
ようやく、徐々に傾斜が緩み、少しずつゴールが近づいていることを2人とも感じてきていた頃、雨がぽつりぽつりと降り始めた。岳沢小屋に到着するころにはだいぶ強くなってきていた。
深夜のテントでは、先生と塾長が冷えたビールを用意して迎えてくれた。奥明神沢から届くヘッドライトを見守ってくれていたらしい。塾長は、日中に岳沢から奥明神沢経由で前穂山頂を往復したが、雪の状態が良く、時間もかからず楽だったとのことだった。
先生が、会長へ下山メールを送って下さっていたことをあとで知った(夜通し下山を待っていた会長にも、たいへんな心配をかけしてしまっていた)。今後、すこしづつであっても、もっともっと力をつけていかなければならないことを思い、皆で1日を振り返り、テント内の安心感に満たされ、就寝した。
6日 岳沢小屋〜上高地〜沢渡〜帰宅
昨夜の就寝は、深夜3時ころだったが、朝明るくなれば自然と目が覚めた。昨夜からの雨は続いていたが、本降りではなかった。
ゆっくり起きて、テントを撤収。9時ころには下山開始。一般登山道だが、雨に濡れたがれ場や、崩れそうな雪渓などで足を取られないように、集中を切らさずに進む。
お昼ころ上高地に到着。雨は降り続いて、なにもかも濡れてしまったような状態になった。
帰りもタクシーを手配したが、どうも歓迎されていない印象だった。乾いた着替えなどをしっかり準備しておく必要があった。
沢渡に移動後、竜島温泉と長野のラーメンチェーン店のテンホウに立ち寄り、帰路についた。